中英語アーサー王ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』
岡本 広毅(立命館大学准教授)
| はじめに |
|
『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) は、14世紀後半に書かれたとされる中世アーサー王物語の一つです。本作品は、古い時代から伝わっていた韻律法(頭韻)で書かれている韻文で、合計101連、全2530行に渡ります。作者は不詳ですが、語彙・文体等の研究から同写本内に収録されている Pearl 『真珠』、 Patience 『忍耐』、 Cleanness 『純潔』の作者と同一人物であると考えられています。(それゆえ、研究者の間では「ガウェイン詩人」「パール詩人」と呼ぶことがあります)
使用言語は「英語」ですが、本作品は成立から500年以上の時を経ていることと、イングランドの北西ミッドランド地域(チェッシャー・ランカシャー周辺)の英語で書かれているため、難解だという印象を持たれています。とはいうものの、本作品の評価は中世英文学史上、目を見張るものがあります。本学会元会長の慶應義塾大学名誉教授・髙宮利行先生の言、「中世英文学の傑作をひとつだけ挙げよと言われれば、わたしは躊躇なく14世紀後半に書かれた騎士ロマンス『サー・ガウェインと緑の騎士』を挙げたい」[1] は、その顕著なものでしょう。 今回は、14世紀末にイングランドに誕生した英文学史に燦然と輝く傑作『ガウェイン卿と緑の騎士』について紹介したいと思います。 |
| あらすじ |
|
まずは本作品のあらすじをⅣ部に分けて紹介します。 Ⅰ クリスマスのある日。王都キャメロットにはアーサー王をはじめ、宮廷人や騎士たちが祝宴を催すため集まっていた。そこへ突如現れたのが全身緑色の大男、緑の騎士である。異様な出で立ちに静まり返る宮廷。静寂を割るように彼が口にしたのは、なんとも数奇な提案「互いの首」を賭けたクリスマス・ゲームを楽しもうというものだった。首切り先攻権が与えられたのはアーサー王側。ただ先攻側には条件がある。一年後、「緑の礼拝堂」と呼ばれる場所にて、同じ目に遭わなければならないというものだ。アーサー王たちは戸惑いながらも蔑まれたことにいきり立ち勝利を確信し、クリスマス・ゲームを受け入れることを決めた。 アーサー王自らがゲームを遂行しようとしたその時である。甥のガウェイン卿が我こそはと進み出て、緑の騎士の首を切り落とす。転がり落ちた首を足蹴にする宮廷人たち。事態は事なきを得たかに見えた... しかし、これは終わりではなかった。全ての始まりだったのである。首無き緑の騎士は切られた首を難なく拾い上げ、一年後の約束を確認するとキャメロットを後にしたのである。  なんなく緑の騎士の首を切り落とすガウェイン卿。しかしこれこそが試練の始まりに・・・ Ⅱ 一年後、ガウェイン卿は約束の地「緑の礼拝堂」へ向かって旅立った。円卓の騎士として、死は覚悟の上で、使命を遂行しなければならない。緑の騎士の情報を求め、北ウェールズ付近からイングランド北西部の荒野を尋ねまわるが、有力情報は皆無。厳しい冬の寒さがこたえ、孤独の騎士は宿を求め彷徨っていた。そんな最中(聖母マリアへの祈りが届いたのか)、眼前に見事な城館が現れる。城の主人から逗留を許されたガウェインは、自らの名前と出自を名乗った。城内は歓喜の渦に。こぞって円卓の騎士の優雅な振る舞いや、宮廷作法を学ぼうとする。丁重なもてなしを受けたガウェインは、束の間の安息を得るのだが、ついには旅の目的を主人に告げ、「緑の礼拝堂」の所在を尋ねる。主人はその場所を知っているという。まだ約束の日までは時間があるので、それまで城に留まるよう勧めた。ガウェインはさらにもう数日、滞在することにした。その間、二人は一つの取り決めをした。その取り決めとは、主人が毎朝、狩猟で得る獲物とガウェインが城の中で過ごす際に「得たもの」を交換し合おう、という契約であった。ガウェインは快く、これに同意した。 Ⅲ 契約後一日目、夜明けとともに、大勢の家来を引き連れ主人は狩りに出発。標的は鹿だ。主人が屋外で狩りに勤しむ中、ガウェインは屋内で別種の狩りに見舞われることとなる。それは奥方、すなわち主人の妻の誘惑である。突然、部屋へやってくる奥方。(先に述べておくと、城外での「主人の狩り」は、そのまま「奥方による円卓の騎士狩り」として並置されていて、主人の狩猟と獲物の性質と反応が、奥方の狩猟とベッド上でのガウェインの言動や心理と巧みに呼応している。「狩り」と「誘惑」が交互に組み合わされているこの場面は、本作品の妙技として高く評価されている)――彼女は一体何をしにここへ…心中穏やかでないガウェインは、はじめ眠っているふりをするのだが、そう長くは続かない。 瞼を開いた騎士に、人妻はこう言う ――降伏の交渉に応じなければ、あなたを寝台に縛りつけましょう。機転を利かせ騎士は、こう応対する ――あなたの捕虜を解放してください。  寝室で眠るガウェイン卿に対して、城主の奥方が誘惑を仕掛ける・・・ ガウェインにとって寝台は「戦場」となった。[2] 不意の来訪者に困惑しながらも彼女が肉体的な意味での「征服」を望んでいることを徐々に理解していくガウェィン。その側らで、彼女が抱きはじめる疑念を気に掛けた。――あなたは本当にガウェインさまかしら?二人きりの密室で何の行動も起こさない騎士は、本当に「あの噂に聞くガウェイン卿」なのかしら。当の本人は結局、彼女に要求された<口づけ>を与えることで、この場を乗り切るのだが。城に帰ってきた主人は、約束通り、射止めた鹿の肉をガウェイン卿に与えた。騎士も約束通り、主人に<口づけ>をするのだった。 二日目、主人は再び狩りへと出かける。標的は巨大な猪。主人一行が野山を駆け回っている中、ガウェイン卿はまたしても奥方の来訪を受ける。奥方は「ガウェイン卿攻略」を心に誓い、昨日最も打撃を与えたと思われる「問い」から揺さぶりにかかる。――あなたが本当にガウェイン様だとしたら・・・。奥方はガウェイン卿の気高い騎士としての評判と名声を聞いているため、自分の目の前にいる騎士道の権化、つまり「愛の技」の熟練者が、どうしてそれを「実技」という形で披露してくれないのか不思議でならない。一方、ガウェインは温度差を感じつつも、奥方を終始持ち上げながらその場をやり過ごしていく。とはいえ、彼女の行動は腑に落ちない。――奥方は一体何を考えているのだろうか。この日も両者は口づけを交わすことでお別れをする。綿密に解体した猪を持ち帰った主人は、その巨大な首をガウェインに差し出した。ガウェインもお返しに口づけをし、両者の約束が同等に果たされていることを再確認するのだった。 三日目の早朝、主人は最後の狩りに出かける。標的は利口な狐。逃げ回る狐に四苦八苦する主人を余所に、ガウェイン卿は寝床でぬくぬくと眠っている。もちろん、この安眠は長くは続かない。そう、奥方だ。彼女は強硬策にうってでた。胸と肩を部分的に露出した官能的な衣装でドレスアップし、ガウェインの部屋へと向かった。騎士は前日までとは裏腹に奥方を歓待し、その可憐に着飾った優美な姿に胸を躍らせながら、奥方から早々の口づけを受けいれてしまう。二人の関係性はより緊密でプライベートな様相を帯び、[3]ガウェイン卿は追いつめられる。奥方の求愛は熾烈さを極め、ガウェインはその性的な訴えにひれ伏すか、突っぱねるか、その二者択一を迫られることとなった。――拒絶すれば、彼女は自分を野暮な男として嘲ることだろう・・・たしかに彼女への礼儀は大事だ・・・だが、自分をもてなしてくれている城館の主人への裏切りはゆめゆめ許されるものではない。円卓の騎士の心の動揺と葛藤は臨界点を迎えた。結局のところ、ガウェインは奥方の求愛を払いのけ、主人への忠誠を貫く。落胆した人妻ではあったが、腰に巻きつけていた緑の絹の帯を受け取るよう懇願する。贈り物を受け取る気のないガウェインに、奥方は言った。――この帯を身につけていれば、いかなる猛者からも傷つけられ、殺されることはありません。この言葉に気持ちの揺らいだ騎士は、その腰帯を受け取り、三度目の口づけをしてお別れをした。その後、城館に戻ってきた主人を迎えたガウェイン卿は三度の口づけをし、主人は狐の皮を贈り返した。そして、来たる出発を主人に告げ、ガウェインは感謝の言葉とともに寝室へと戻った。 Ⅳ キャメロットでのクリスマス・ゲームから一年。新年の朝、滞在していた城を後にし、ガウェインはついに「緑の礼拝堂」を目指す。いよいよそれと思しき場所にたどり着き、一年ぶりに緑の騎士と再会を果した。ガウェインは「お返しの一撃」を受けるため髪をかき上げ首をあらわにする。緑の騎士は二度、大斧を首の寸前で止め、照準をあわせた三度目、ついにガウェインの首をめがけて振り下ろす。ガウェインは死を覚悟したが、斬首されることなく切り傷を受けるにとどまった。雪一色の大地に自身の血痕を見たガウェインは、すかさず防御態勢に入ったが、一命をとりとめたことに安堵した。 ――約束は果たしたぞ。意気込むガウェイン卿に向かって、緑の騎士は一連の試練の種明かしを始める。なんと、緑の騎士はガウェインが逗留した城の主人で、妻の誘惑も主人が仕組んだものだったのだ!そして三度の首切りは、ガウェインの宮廷での行いに関係したものだという。二度の寸止めは、ガウェインが約束通り屋内で得たものを交換したためであり、三度目に傷を負わせたのは妻の腰帯を交換しなかったから・・・全てはお見通しだったのである。――少しの誠実さに欠けただけ。寛容な主人の振る舞いとは対照的に、ガウェイン卿は顔を真っ赤にし、緑の腰帯を投げ捨て、自らの過ちを悔いた。 主人はベルシラックという名で、緑の騎士の姿は城に住む魔術師モルガン・ル・フェイ(アーサー王の異父姉妹、ガウェインの叔母にあたる)の魔法によるものだったことが明らかとなる。[4] こうして二人は互いの礼節と武勇を称え合い、ベルシラックは今一度、彼の叔母もいる居城での歓待を申し出るが、ガウェインはそれを固辞し、アーサー王の待つ宮殿へと帰路を急いだ。戒めとして緑の腰帯を肩からかけて帰還したガウェインは、忸怩たる思いで自身の過ちを公表した。アーサー王はそんなガウェイン卿を慰め、緑の腰帯は<不実の証>としてではなく、<栄誉の勲章>として祭り、物語は幕を閉じるのである。 |
| 緑の騎士はモンスター? | ||
|---|---|---|
|
中世に書かれた作品には、いわゆる「モンスター」の類いが多く登場します。『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』といった、ファミコン時代のRPG(Role Playing Game)を享受した世代にとって、モンスターは敵で、その大本である「ボス」(通称ラスボス)を倒すことで物語は完結しました。しかし、モンスター=悪のこの構図は、徐々に変化します。例えば、『ドラゴンクエストⅤ』においては、モンスターが仲間の一員になり、名作『クロノトリガー』では「ボス」であった魔王すらパーティの主軸を担い、そして何より、『ポケットモンスター』の大ブームによってモンスターは主人公となりました。榎本眞理子氏は、近年関心を集めるモンスターに関して以下の様に述べています。 |

アーサー王物語はドラゴンクエストやファイナルファンタジーの一つの源泉でもある |
|
|
つまるところモンスターとは他者のことである。それは常に「私」のシャドウとして存在してきた。だが人々は古来自分の外に他者を見いだしてきたのである。そして一方では他者に憧れ、また一方では他者を呪詛し、スケープゴートとしても殺害もしてきた。現代では、その他者が実は「私」の内部にも潜んでいることを我々は知っている。 [5] モンスターは本来「他者」だったのに、その「他者」を自らの中に発見してしまったのが現代感覚なのでしょうか。いずれにしろ、どうやらモンスターは我々にとって至極近い存在になってきていることは明らかです。 さて、話を本作品に戻しましょう。中世イングランドの人々が、モンスターに対するこの「近しい感覚」を共有していなかったとは言い切れません。<緑の騎士>はこの点で実に興味深い存在です。彼はたしかに巨漢で緑一色なわけですから、外見的にモンスター的存在と言えるでしょう。しかし、その全身緑一色の大男が放つ異様さと恐怖に反して、高価なマントや毛皮に意匠を凝らした煌びやかな宝石や刺繍など、貴族文化の一面が散見できます。彼の顎鬚は肩や胸までまるで生い茂った木々のように伸びている一方で、手入れを怠った露骨な野生性よりも、むしろ優雅になびく毛髪の格調高さや、肘のあたりで刈り揃えてあるという洗練さが強調されているのです。またその髪が上腕を覆い隠すしなやかなしぐさは、王が首に羽織るケープのようであるとまで喩えられています。 事実、本作品の緑の騎士は、これまで多くの文人や批評家の心を捉えてきました。『ナルニア国物語』で有名な中世研究者C. S. Lewis はすでに何十年も前に、緑の騎士の本質を次のように表現していました。 緑の騎士は半ば巨人であるが、「ラブリーな」騎士でもある (half giant, yet wholly a “lovely knight”)。老カラマーゾフの悪魔的エネルギーと、『クリスマス・キャロル』に登場する主人の陽気さに溢れている。 [6] |
||

オックスフォード大学の英文科図書館にあるJ.R.R. トールキンの胸像。『ナルニア国物語』の著者C. S. ルイスとは同僚であり、良き友でもあった。 |
緑の騎士の表象は、決して善悪では括り切れない様々な暗示と示唆に富んでいるのです。そのメッセージをどう受け取るかはアーサー王宮廷人、あるいは聴衆次第です。このサスペンス状態は、緑の騎士は本名や背景、住まいなどについて何も語ることなく序盤以降、姿を消すことによっても高められています。Sarah Stanbury という学者が本作品を「14世紀の推理小説」と呼ぶのも無理はありません。[7] 果たして犯人の正体は何者なのか、味方なのか敵なのか。単なるモンスターの領域を超越した本作の緑の騎士は、その不在感も含め抜群の存在感を発揮しています。 | |
| ガウェイン卿の人間味と恥 |
|
本作品の魅力の一つは、高潔なる騎士像が崩壊し、実際にはただの無力な一人間であることが露呈してしまうところにあります。ガウェイン卿は、完全無欠の騎士ではなく、自分の命が助かるとなれば主人への忠誠心を犠牲にする自分本位な一面を持っているのです。優先順位を自分に置く過程で、悩み、もがき苦しみ、そして最後には内省し、反省する人間味が溢れる姿に共感を覚えます。こうした「内省」の奥深さは、高貴な理想や精神をもたねばならない円卓の騎士ガウェイン卿だからこそ、より一層劇的に表されるのです。<理想>と<現実>に板挟みとなり葛藤する一人間の有り様、あるいは<人間としての弱さ>の表出は、紛れもなく本作品の主題であり、魅力の一つです。 ガウェインの人間味が最も滲み出ているように感じるのは、緑の騎士から全ての種明かしを聞いた後の、彼の言動においてです。 Þat oþer stif mon in study stod a gret whyle, So agreued for greme he gryed withinne; Alle þe blode of his brest blende in his face, Þat al he schrank for schome þat þe schalk talked. (2369-72) 相手の騎士(ガウェイン卿)はしばらくその場に立ち尽くし 屈辱に塗れ 、心中身震いがした 胸から血がどっと顔へと溢れ その男が話したことに恥じ入り、身が竦みあがった ――自分は試されていたのか、全ては見透かされていたのか。極度の動揺を隠し切れないガウェインはその後、自己弁護に躍起になります。顔を真っ赤に染め上げたガウェインは開口一番、「臆病と貪欲に呪いあれ!」と罵倒し、それらの悪徳を二人称代名詞複数の ”You” (お前たち) と呼びます。その後、なぜか怒りの矛先を緑の帯へと向け、「この不実の帯を見よ。偽りよ、地に落ちろ!」と叫びます。悪徳という外部の何かが自分に憑依しただけで、これは「本来の自分」ではないとでも言いたげです。 [8] 一方、緑の騎士は彼に非はないことを諭し、自分の館に戻って宴を楽しもうと提案します。――そなたの仇敵であった私の妻とも仲直りできるのだから。この誘いにガウェインは「ノー」と即答します。奥方との一連のやりとりが主人に筒抜けになっていたことを知った今、彼には「今更奥方に会っていられるか」という屈辱にも似た気持ちがあったのではないでしょうか。(あるいは、まんまと術中にはまってしまった自分自身の愚かさに憤懣やるかたなしといったところでしょうか。)挙句の果てには、アダムやソロモン王、サムソンといった女性に惑わされた聖書の中の男性陣に自己を重ね、この度の件の正当化を図る始末です。――私も騙されましたけれども、先人を見れば多少の言い訳が立ちましょう。このように、ひどく取り乱し、半ば開き直りともとれる発言を繰り返しながらそれでもいい恰好を見せようとするガウェイン卿を見ると、「この人、相当痛いところを突かれたのだな」と思わざるを得ません。 それでも、ガウェイン卿は最終的に反省しているとは思います。アーサー王の宮殿に戻った彼は、個人的な失態を公の下に晒すという勇気のある行動に出ているのです。 He tened quen he schulde telle, He groned for gref and grame; Þe blod in his face con melle, When he hit schulde schewe, for schame. ‘Lo! lorde,’ quoþ þe leude, and þe lace hondeled, ‘Þis is þe bende of þis blame I bere in my nek, Þis is þe laþe and þe losse þat I laȝt haue Of couardise and couetyse þat I haf caȝt þare; (2501-9) 真実を話すことは拷問であった 苦しみと屈辱に呻き 顔は真っ赤に染まった 彼は恥を凌ぎつつ、それを見せた 「王よ、これをご覧ください。」 ガウェイン卿は帯を掴んだ 「私が首に着けているこれこそが罪の帯 これは私が受けた傷 かの地で臆病と貪欲に屈した証・・・ 緑の騎士の面前で真相を知った様子とほぼ同様の面持ちで、ガウェイン卿は緑の腰帯を提示します。ガウェインは一連の不面目な体験を隠すこともできたはずです。しかしそうはせず、寝室での至極プライベートな経験から派生した出来事を一つ一つ話し、全てを白日の下にさらしてしまうのです。 羞恥を晒し、同胞たちにそれを「開示する」姿勢は、理想の騎士像から転落した円卓の騎士としての最後の矜持と見受けられます。しかし裏を返せばそれは、罪悪から早く解き放たれたいという自己の欲求を満たすための行動ともとれます。それは、いたずらをしてしまった子供が、泣きながら両親や先生に謝る姿のように。いずれにせよ、騎士道に同居する赤子のように無垢な良心の呵責などが、円卓の騎士ガウェインの<人間味>をより増幅させる結果になっているのです。 |
| 色彩のコントラスト | ||
|---|---|---|
|
本作品における色彩表現の豊かさは注目に値します。その中で、強烈な印象を放つ緑の騎士。中世において緑色は生命、再生、若さ、あるいは異界などを連想させる色でした。また緑の騎士の正体に関しては、植物神や太陽神、野人や死神、悪魔など、民俗学的・神話学的視点から様々な解釈がなされています。[9] <赤>と<白>のコントラストが鮮やかに表現される場面があります。緑の騎士からの一撃を受けた直後のシーンは以下のように記されます。 Þe scharp schrank to þe flesche þurȝ þe schyre grece, Þat þe schene blod ouer his schulderes schot to þe erþe; And quen þe burne seȝ þe blode blenk on þe snawe, He sprit forth spenne-fote more þen a spere lenþe... (2313-16) 鋭利な刃が皮膚をつき抜け肉へと達した 鮮血が彼(ガウェイン卿)の両肩を伝って流れ大地へと落ちた 騎士は雪の上でその血が光るのを見ると 跳び下がって槍一本以上の距離をとった |
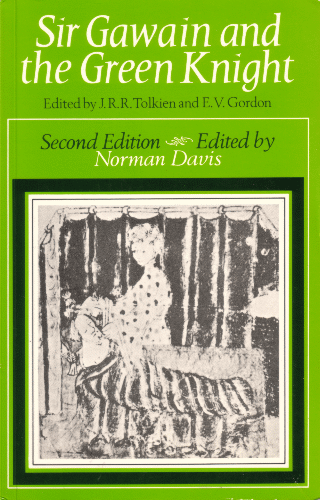
1925年にJ.R.R Tolkien と E. V. Gordon によって出版された校訂本(1967年にNorman Davis によって改訂)。現在も最良の校訂本として使用されており、装丁はやっぱりグリーン! |
|
|
傷口から飛び散ったガウェインの鮮血 (þe blode) は、大地を覆う雪 (þe snawe) へと零れ落ちます。騎士の<真っ赤な血>が、<真っ白な雪>に溶け込むという、この色の対比は実に鮮やかです。『中世英語英文学Ⅰ―その言語と文化の特質―』の著者である菊池清明先生は、本作品における色彩の対照の重要性をとりわけ指摘していますが、この場面はその最たるものであると述べています。ガウェイン自身が実際に自身の血だまりを見た(“seȝ”)とあります。中世の冒険譚などでは、吹雪や霧は異世界への合図として考えられることもあります。[10] 本作品でもそうした要素は色濃く、例えばガウェインが「緑の礼拝堂」へ出発する日は、突如天候が崩れ、雪が土地を覆いつくし、まるで異世界に導かれていくかのように描かれています。しかし、真っ白な積雪の上に滲み込んだガウェインの真っ赤な血は、彼のリアルな肉体よりほとばしった血潮に他なりません。圧倒的な現実感が、色彩の効果により強調されるわけです。それゆえ、自らの血を「見た」ガウェイン卿が次にとった行動、つまり、「すぐさま緑の騎士の次の一撃に備え、防御体制に入る」姿は、実に現実的な対応です。<赤>と<白>の色彩のコントラストは、ガウェイン卿の生命を自覚させ、本作品に横たわる「生への渇望」という主題を劇的に演出しています。 |
||
| トロイの末裔として――自分探しの旅の結末 | ||
|---|---|---|
|
「アーサー王宮廷において、宮廷人や騎士たちが陽気な一時を過ごしている。」これは中世アーサー王物語の常套句的な始まりです。しかし、本作品はこのような始まりの前に、古代トロイ戦争への言及があります。これまで触れてきませんでしたが、本作品の冒頭を飾るのは、ギリシャ軍によるトロイの陥落のエピソードです。パリスによるヘレン誘拐が引き金となって起こったあの古代文明国の一大戦争が本作品のプロローグとして記されているのです。トロイ崩壊が本作品とどのように関係するのでしょうか?
12世紀のイングランドで、ジェフリー・オブ・モンマスという人物は、ブリテン島の建国者をトロイの戦禍から逃れたアエネアスの子孫のブルータスとし、アーサー王の祖先はそのブルータスであると提唱しました。(すなわちブリテン島の名称は、このブルータスに由来するとされました。)ブリテン島の建国神話をトロイの英雄と結びつけた彼の書物は、瞬く間にヨーロッパ諸国へと広がり、トロイへと遡源する歴史観は、各国のアイデンティティを規定する上で魅力的な物語となりました。トロイの戦塵からローマをはじめとする西方諸国の主要な都市が建設される模様が、本作品の冒頭でも描き出されています。 SIÞEN þe sege and þe assaut watz sesed at Troye, Þe borȝ brittened and brent to brondeȝ and askez, Þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wroȝt Watz tried for his tricherie, þe trewest on erthe: Hit watz Ennias þe athel, and his highe kynde, Þat siþen depreced prouinces, and patrounes bicome Welneȝe of al þe wele in þe west iles. … And fer ouer þe French flod Felix Brutus On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez wyth wynne, Where werre and wrake and wonder Bi syþez hatz wont þerinne, And oft boþe blysse and blunder Ful skete hatz skyfted synne. Ande quen þis Bretayn watz bigged bi þis burn rych, Bolde bredden þerinne, baret þat lofden, In mony turned tyme tene þat wroȝten. (1-22) |
||
|
トロイの包囲と攻撃が終わり、 城市は瓦解し、戦禍の灰と化した 謀反を起こした反逆者は 裁きを受けたが、この世で高潔であった それは気高きアエネアスとその高貴なる一族 彼らはその後、各王国を征服し、土地を治め、 西方諸国の殆ど全ての富を手にした ・・・ フランスの海を越えたブルータスは 広大な土地にブリテンの国を建てた そこで戦や争いが 絶えず起こった 至福と災難が 交互に繰り返し続いた 高貴なその戦士によってブリテンが建国されると そこは戦に熱狂する輩の温床となり 彼らは度々混乱を巻き起こした |

|
|
|
12世紀においてトロイを祖先とすることは、一国の高貴なる起源を誇示するものでした。しかし、14世紀末の本作品ではどうでしょうか。アエネアスの末裔であるブルータスはブリテン島を樹立するも、その土地に秩序と平和をもたらすことはありません。彼らの入植は、“bliss and blunder” (至福と災難が交互に続く)というように、度重なる争乱の引き金になります。そこは戦に熱狂する輩の温床となり、彼らは度々混乱を巻き起こしたのです。こうした冒頭の不穏な余韻の中で、アーサー王宮廷の物語が幕を開けるのです。 こうしたトロイ人による建国神話の枠組みは、本作品の独自の要素と言えます。そうなると、この後のガウェイン卿の旅は、アエネアスとその子孫の西方諸国への旅のパラレルとして見ることも可能です。トロイの滅亡によって、文明の<中心>が<周縁>の西方諸国へと推移していくように、ガウェインはアーサー王宮殿という<ホーム>から、イングランド北西部の奥地という<アウェイ>へと向かいます。ガウェイン卿を行く先で待っていたのは、緑の騎士を操る黒幕モルガン・ル・フェイでした。この事実によって本作品はアーサー王一族の内輪の物語となります。トロイに遡るアーサー王一族は、その血統的呪縛からは逃れることができないのです。物語の序盤、ガウェインは緑の騎士への一撃を前に、自分の血筋を深く気にかけている場面があります。彼は「自分は最も弱く知恵も浅いが、アーサー王が自分の叔父だからもてはやされるのだ」という自虐めいた発言をしています。王の甥であるガウェインは、ある種の後ろめたさを払拭したかったのではないでしょうか。伯父アーサーの庇護を脱し、一族に着せられた全ての装束を剥ぎ取って、自分に一体何が残るのか、一人荒野に駆り出たガウェイン卿にとって、それは<自分探しの旅>と同義でした。しかし、最終的に事実として彼に跳ね返ってきたのは、皮肉にもその血統的トラウマでした。モルガンという自分の叔母が全ての仕掛け人であった事実は、彼にとって衝撃的な結末だったはずです。 フロイトは言います。不気味なもの、おぞましく疎遠なものとは、実は一度抑圧を経て再び戻ってきた慣れ親しんだものである、と。ニーチェは言います。「怪物とたたかう者は、みずからも怪物とならぬようにこころせよ。なんじが久しく深淵を見入るとき、深淵もまたなんじを見入るのである」と。 [11]アーサー王の宮廷人にとって一連の出来事は、驚異に満ち、奇怪で、理解の範疇を越えた経験でした。一見数奇に思われた出来事もその実、全てモルガンという身内の人間が引き起こしたものだったのです。ガウェイン卿は人間臭さを露呈しつつも、自身の過ちを深く懺悔します。怪物と対峙した彼は「自らが怪物とならぬよう」注意したのです。しかしガウェイン卿は、文字通りモルガンや緑の騎士という怪物染みた存在を前にし、そこに映る<別の怪物>の存在に気づいたのではないでしょうか。すなわち、彼は自分の属するアーサー王国内にその怪物性を見出してしまったのです。 アーサー王のいる宮廷に戻ったガウェインは、羞恥心を堪え自ら罪を公表します。しかし、アーサー王をはじめとする宮廷人や騎士は彼らの同胞の過ちと真摯に向き合わず、ただ笑って宥めるばかりです。それに対するガウェインの反応は記されることなく、物語は再びトロイの崩壊とブリテン島の建国に触れ、幕を閉じます。 決死の告白は一笑に付され、最後には沈黙を余儀なくされるガウェイン卿。冒頭と末尾に設けられたトロイ陥落への枠組みを通して本作品を見た場合、ガウェイン卿の最後の沈黙は実に暗示的ではないでしょうか。すなわち、アーサー王帝国の個を黙らせてしまう(ここでは一騎士の改悛の言葉に耳を傾けることを怠るという意味で)<怪物性>こそが、まるでトロイ滅亡のようにその後のキャメロット崩壊の火種となるという、詩人の批判的眼差しがそこには込められているように思われます。ガウェイン卿の冒険は、トロイに遡る一民族の命運を握る旅でした。この点で、本作品は必ずしもアーサー王物語ロマンスという枠組みに限定されることのない、ガウェイン卿を主役とした古代ラテン文学へと連なる一大叙事詩ということができるかもしれません。 |
||
| Notes |
^1. 髙宮 180. また、その他の作品と比較され、以下の様に続けられています。「なぜ有名なチョーサーの『カンタベリー物語』でないかといえば、あれは個々の作品の出来もよく、登場人物とそれぞれが話す物語がうまく連携しているといえるが、いかんせん未完に終わっているのである。また15世紀後半にサー・トマス・マロリーが書いた『アーサー王の死』については、現代人でも面白く読めるし、19世紀以降の再話に多大な影響を与えた点は認めるにしても、所詮はフランス語の散文アーサー王物語を英語に翻案して、脈絡をつけたという印象はぬぐいがたい」 (180)。^2. Mann 111.^3. Putter (1995) 138.^4. このあたりの親族関係は作品によって若干異なる。^5. 榎本 26.^6. Lewis 219.^7. Stanbury 109.^8. Pearsall 357.^9. 緑の騎士の正体を明らかにしようとする研究の変遷に関しては、生地、特に第八章『サー・ガウェインと緑の騎士――緑の騎士の正体――)に詳しい。^10. Puhvel 225.^11. この点は、2008年度日本中世英語英文学会において私の研究発表の後、12月17日に小宮真樹子先生からメールでご指摘いただいた。 |
| 参考文献 |
|
池上忠弘, 訳. 『サー・ガウェインと緑の騎士』 東京: 専修大学出版局, 2009.
境田進, 訳. 『ガウェイン詩人全訳詩集』 東京: 小川図書, 1992.
J.R.R.トールキン著; 山本史郎, 訳. 『サー・ガウェインと緑の騎士: トールキンのアーサー王物語』 東京: 原書房, 2003.
Armitage, Simon, tr.
Sir Gawain and the Green Knight. New York: W.W. Norton, 2007.
Borroff, Marie, tr.
Sir Gawain and the Green Knight: A New Verse Translation. New York: W.W. Norton, 1967.
Finch, Casey, tr.
The Complete Works of the Pearl Poet. Berkeley: University of California Press, 1993.
Stone, Brian, tr.
Sir Gawain and the Green Knight. London: Penguin, 1959 and 1974.
Tolkien, J.R.R., tr.
Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, and Sir Orfeo. London: Allen, 1975 & 1990.
Burrow, J. A., and Thorlac Turville-Petre,
A Book of Middle English. 3rd ed. Oxford: Blackwell, 2004.
Putter, Ad, and Myra Stokes, eds,
The Works of Gawain Poet: Sir Gawain and the Green Knight, Pearl, Cleanness, Patience. London: Penguin, 2014. Print.
Tolkien, J. R. R., and E. V. Gordon, Eds.
Sir Gawain and the Green Knight. 2nd ed. Rev. by Norman Davis. Oxford: Oxford Clarendon P, 1967.
榎本眞理子, 『イギリス小説のモンスターたち 怪物・女・エイリアン』 東京:彩流社, 2001.
生地竹郎, 『チョーサーとその周辺』 東京:文理書院, 1968.
菊池清明, 『中世英語英文学Ⅰ―その言語と文化の特質―』 横浜:春風社, 2015.
髙宮利行, 「中世英文学におけるコミック・リリーフ―『サー・ガウェインと緑の騎士』のフットボールの場合」『芸文研究』 88, 2005. 180-84.
小路邦子, 「ガウェインの誕生と幼年時代」 『剣と愛と 中世ロマニアの文学』 中央大学人文科学研究所研究叢書 34. 八王子:中央大学出版部, 2004. 93-116.
田口まゆみ・松田隆美, 「『ガウェイン』詩人」 『中世イギリス文学入門―研究と文献案内』 高宮利行・松田隆美, 編. 『中世イギリス文学入門: 研究と文献案内』 東京: 雄松堂, 2008. pp.171-179.
田口まゆみ, 「『ガウェイン卿と緑の騎士』の諧謔と厳粛」 『尾形敏彦・森本佳樹両教授退官記念論文集』 奈良女子大学文学部英語・英米文学科尾形・森本両教授退官記念論文集刊行会編. 京都:山口書店, 1985. 14-25.
Anderson, J. J.
Language and Imagination in the Gawain Poems. Manchester: Manchester UP, 2005.
Bennett, Michael. “Sir Gawain and the Green Knight and the Literary Achievement of the North-West Midlands: the Historical Background.”
Journal of Medieval history 5 (1979): 63-88.
Benson, Larry D.
Art and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight. New Brunswick: Rutgers UP, 1965.
Bergner, H. “The Two Courts: Two Modes of Existence in Sir Gawain and the Green Knight.”
English Studies 67 (1986): 401-16.
Brewer, Elisabeth.
Sir Gawain and the Green Knight: Sources and Analogues. 2nd ed. Rochester: D. S. Brewer, 1992.
Elliott, Ralph W. V.
The Gawain Country: Essays on the Topography of Middle English Alliterative Poetry. Leeds: U of Leeds, School of English, 1984.
Federico, Sylvia.
New Troy: Fantasies of Empire in the Late Middle Ages. Minneapolis: U of Minnesota P, 2003.
Finlayson, John. “The Expectations of Romance in Sir Gawain and the Green Knight.”
Genre 12 (1979): 1-24.
Hanna, Ralph. “Alliterative Poetry.”
The Cambridge History of Medieval English Literature. Ed. David Wallace. Cambridge: CUP, 1999.
Knight, Rhonda. “All Dressed Up with Someplace to Go: Regional Identity in Sir Gawain and the Green Knight.”
Studies in the Age of Chaucer 25 (2003): 259-84.
Lewis, C. S. “The Anthropological Approach.”
English and Medieval Studies Presented to J. R. R Tolkien on the Occasion of His Seventieth Birthday. Eds. Norman Davis and C. L. Wrenn. London: Allen and Unwin, 1962. 219-23.
Mann, Jill. “Sir Gawain and the Romance Hero.”
Heroes and Heroines in Medieval English Literature: a Festschrift Presented to André Crépin on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday. Ed. Leo Carruthers. Rochester: Boydell & Brewer, 1994. 105-17.
Matsuda, Takami. “Sir Gawain and the Green Knight and St Patrick’s Purgatory.”
English Studies 88 (2007): 497-505.
Mills, David. “An Analysis of the Temptation Scene in
Sir Gawain and the Green Knight.”
JEGP 67 (1968): 612-30.
Mueller, Alex.
Translating Troy: Provincial Politics in Alliterative Romance. Ohio: Ohio State UP, 2013.
Okamoto, Hiroki. “Gawain’s Treachery on the Bed: Trojan Ancestry and Territory in
Sir Gawain and the Green Knight.”
Studies in English Literature 56 (2015): 19-37.
Pearsall, Derek. “Courtesy and Chivalry in
Sir Gawain and the Green Knight: the Order of Shame and the Invention of Embarrassment.”
A Companion to the Gawain Poet. Eds. Derek Brewer and Jonathan Gibson. Woodbridge: D.S Brewer, 1997, 351-62.
Puhvel, Martin. “Snow and Mist in
Sir Gawain and the Green Knight: Portents of the Otherworld?”
Folklore 89 (1978): 224-28.
Putter, Ad.
Sir Gawain and the Green Knight and Medieval French Arthurian Romance. Oxford: Clarendon. 1995.
---. An Introduction to the Gawain-poet. London: Longman, 1996.
Stanbury, Sarah. Seeing the Gawain-poet: Description and the Act of Perception. Philadelphia: University of Philadelphia, 1991.
|
|
|
2023年12月3日、「サラセンの騎士パロミデス:キリスト教世界における他者」を掲載いたしました。
2022年11月4日、「『花咲く谷のダーニエル』(デア・シュトリッカー)」を掲載いたしました。
2022年9月26日、「スペインにおけるアーサー王の伝統:中世から『ドン・キホーテ』まで」を掲載いたしました。
2022年3月31日、「『トリスタン』の愛についての一考察」を掲載いたしました。
2020年6月16日、「Prose Brut Chronicle-『散文ブルート』におけるアーサーとその影響-」 を掲載いたしました。
2020年6月16日、「中世仏語ロマンス『Le roman de Silence』(小川真理)」を掲載いたしました。
2020年3月8日、「『ティトゥレル』Titurel―「誠のある真実のミンネ」と明かされない謎―」 を掲載いたしました。
2020年2月25日、「聖杯」 を掲載いたしました。
2020年2月25日、「『トリスタン』(ゴットフリート・フォン・シュトラースブルク)」 を掲載いたしました。
2019年8月21日、「「アーサー王物語」への神話学的アプローチ―「グラアルの行列」の解釈を例に―」 を掲載いたしました。
2019年5月13日、「『狐物語』とトリスタン伝説、そしてアーサー王伝説」を掲載いたしました。
2018年10月15日、「こんなところでアーサー王伝説に遭遇!」を掲載いたしました。
2018年9月21日、「アニメーションやゲームに登場するアーサー王物語と円卓の騎士について」を掲載いたしました。
2018年9月15日、「<映画の中のアーサー王伝説1> 『スター・ウォーズ』:宇宙版アーサー王伝説 」を掲載いたしました。
2018年8月23日、「円卓」を掲載いたしました。
2018年8月6日、「『アーサー王の死』の著者サー・トマス・マロリーについて」を掲載いたしました。
2017年12月25日、「北欧におけるアーサー王物語」を掲載いたしました。
2016年12月13日、「ジェフリー・オブ・モンマス」を掲載いたしました。
2016年12月8日、「魔法使いマーリン」と「中英語アーサー王ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』」を掲載いたしました。
